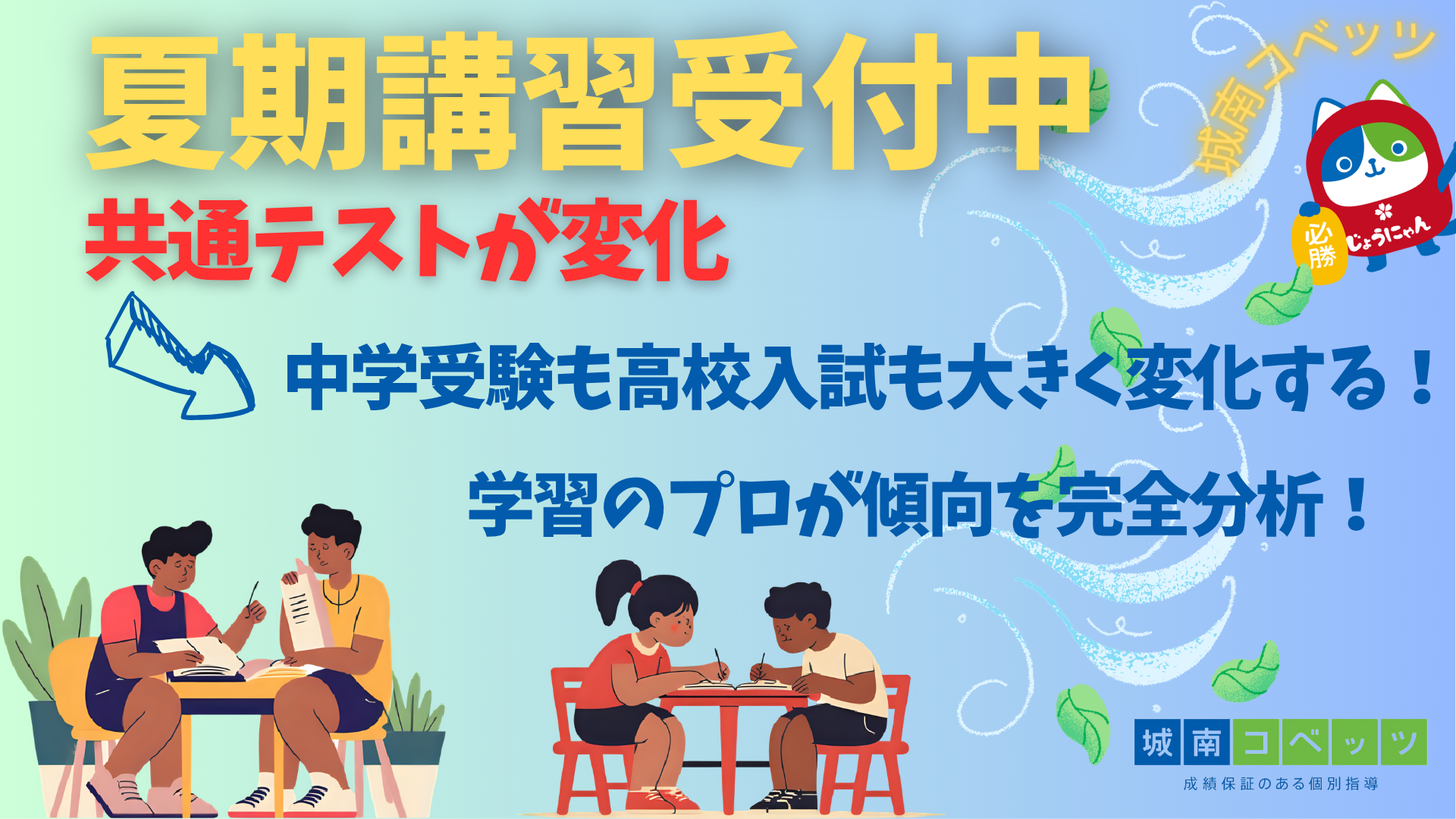2025.06.17


こちらの一番上にあるのがR7年度の千葉県入試の平均点です。
予想より低かったですね・・・。
英語が47.1点というのは、かなり低いです。
こちらがR3年からの平均点推移です。
マークシートが採用されたR6年のときに、R5年と比較して平均が上がりすぎたので若干調整したという流れでしょうか。
千葉県が公表した入試結果によると、2024年度の高校入試は、前年度に比べて英語と社会の平均点が大幅に低下しました。特に英語は9.3点、社会は5.8点も下がり、多くの受験生が苦戦したことがうかがえます。一方で国語と数学は平均点が上昇し、理科はほぼ横ばいでした。
各教科の分析と傾向
国語:平均点上昇、記述力向上が課題
国語の平均点は56.6点で、前年から6.2点上昇しました。聞き取り問題や漢字の読み、歴史的仮名遣いなど、基礎的な知識を問う問題の正答率が高かったことが要因と考えられます。
しかし、「文章の内容の理解と表現」や「登場人物の心情の理解」といった記述式の問題では、例年通り正答率が低く、無答率も高い傾向が見られました。これは全国学力・学習状況調査の結果とも一致しており、読解力や表現力のさらなる育成が求められます。
【指導のポイント】
- 多様な文章に触れ、語彙を豊かにし、文脈を正確に読み取る力を養う。
- 複数資料を分析し、情報を整理して自分の考えを記述する練習を繰り返す。
- 授業のまとめや感想を簡潔に書く活動を通して、記述への抵抗感をなくす。
社会:平均点大幅低下、資料活用力と表現力が鍵
社会の平均点は51.7点で、前年から5.8点低下しました。現代社会の諸課題への関心や理解、資料を活用した判断・分析力、そして思考を表現する力が問われる問題が多く出題されました。
正答率が高かったのは「防災への意識と取り組み」や「グローバル化」に関する問題でしたが、「フィヨルドの定義」や「首長の解職(リコール)」、「信長の城下町政策」といった、知識だけでなく深い理解を求める問題や記述式の問題で正答率が低く、無答率も高かったです。
【指導のポイント】
- 地理分野:地図や統計資料を読み解き、地理的事象の仕組みや原因、地域間の関連性を考察する。
- 歴史分野:歴史の大きな流れをつかみ、個別の事象の関連性や因果関係を自分の言葉で表現する。
- 公民分野:新聞やインターネットなどを活用し、時事問題への関心を高め、複数の資料を関連付けて考察する。
数学:平均点微増、図形・関数・確率の応用力が課題
数学の平均点は52.0点で、前年から0.1点とほぼ横ばいでした。大問1の基本的な問題は正答率が高かったものの、関数の応用問題や、図形の相似の証明とその応用、場合の数と確率の複雑な問題で正答率が低く、無答率が高い傾向が見られました。
特に、「関数(平行四辺形)」や「平面図形(相似の応用)」といった、複数の知識を組み合わせて思考する問題で苦戦した受験生が多かったようです。
【指導のポイント】
- 数と式:方程式の解を吟味するなど、具体的な事象と関連付けて学習を深める。
- 図形:観察や操作を通して作図や図形の関係を考察し、論理的な思考力を養う。
- 関数:具体的な事象との関わりを持たせながら、式やグラフを用いて他者に説明する機会を設ける。
- データの活用:日常生活や社会に関わる問題を取り上げ、説明し伝え合うことで理解を深める。
理科:平均点低下、作図・計算問題に課題
理科の平均点は55.4点で、前年から3.7点低下しました。「観察・実験を題材とした問題」や「身近な生活に関わりのある問題」が多く出題され、作図やグラフの問題も昨年度より増加しました。
生物的領域は比較的正答率が高かったものの、物理的領域と地学的領域が低かったです。特に、「水中の物体が見えるときの光の道すじ〔作図〕」や「加湿器が放出した水蒸気量〔計算〕」、「光電池パネルの設置角度〔計算〕」といった作図や計算を要する問題で正答率が低く、無答率も高い傾向が見られました。
【指導のポイント】
- 物理的領域:実験結果の仕組みを法則に基づいて思考し、作図や文章でまとめる練習を行う。
- 化学的領域:化学式や計算を基に実験結果を考察し、日常生活との関連性を理解する。
- 生物的領域:観察・実験を通して特徴を体系的に整理し、共通点や相違点を理解する。
- 地学的領域:観察・実験結果を基にグラフを作成したり、計算で比較したりして考察する。
英語:平均点大幅低下、語順整序と記述式問題が課題
英語の平均点は47.1点で、前年から9.3点と大きく低下しました。リスニングは比較的正答率が高かったものの、「語順整序("such as"を使った文)」や「内容を踏まえ、空所に英語を補充する」といった問題で正答率が極めて低く、無答率も高かったことが、平均点低下の大きな要因と考えられます。
特に、既習の事項を活用し、対話の流れや英文の内容を理解した上で正確な英文を作成する力が不足していることが浮き彫りになりました。また、英作文問題も無答率が10%以上と高かったです。
【指導のポイント】
- 聞くこと:英語の音声を認識する力を育て、聞き取った情報をまとめ、概要や要点を話して伝える活動を行う。
- 語彙・表現:既習の語彙や表現を繰り返し活用し、自分の考えを表現できるレベルまで定着させる。
- 読むこと:多様な英文に触れ、目的に応じた様々な読み取り方を指導する。読んだ内容を簡潔に伝え、意見を述べる活動を通して、統合的な英語の活用力を育成する。
- 書くこと:口頭練習を十分に行ってから書く活動をするなど、間違いを恐れずに取り組める工夫をする。
今後の学習への示唆
今回の入試結果から、千葉県では、知識の暗記だけでなく、それを活用して思考し、表現する力がより重視されていることが改めて示されました。特に、記述式の問題や作図、計算問題、そして英語の語順整序や自由英作文といった応用力が問われる問題で、多くの受験生が苦戦しています。
今後の学習においては、各教科の基礎を固めることはもちろんのこと、複数の情報を組み合わせて考察する力、自分の考えを論理的に表現する力、そして文章や資料から必要な情報を正確に読み取る力を意識的に鍛えることが重要となるでしょう。日頃から、単に問題を解くだけでなく、その背景にある原理や仕組みを理解し、自分の言葉で説明する練習を積極的に取り入れていくことが、合格への鍵となりそうです。