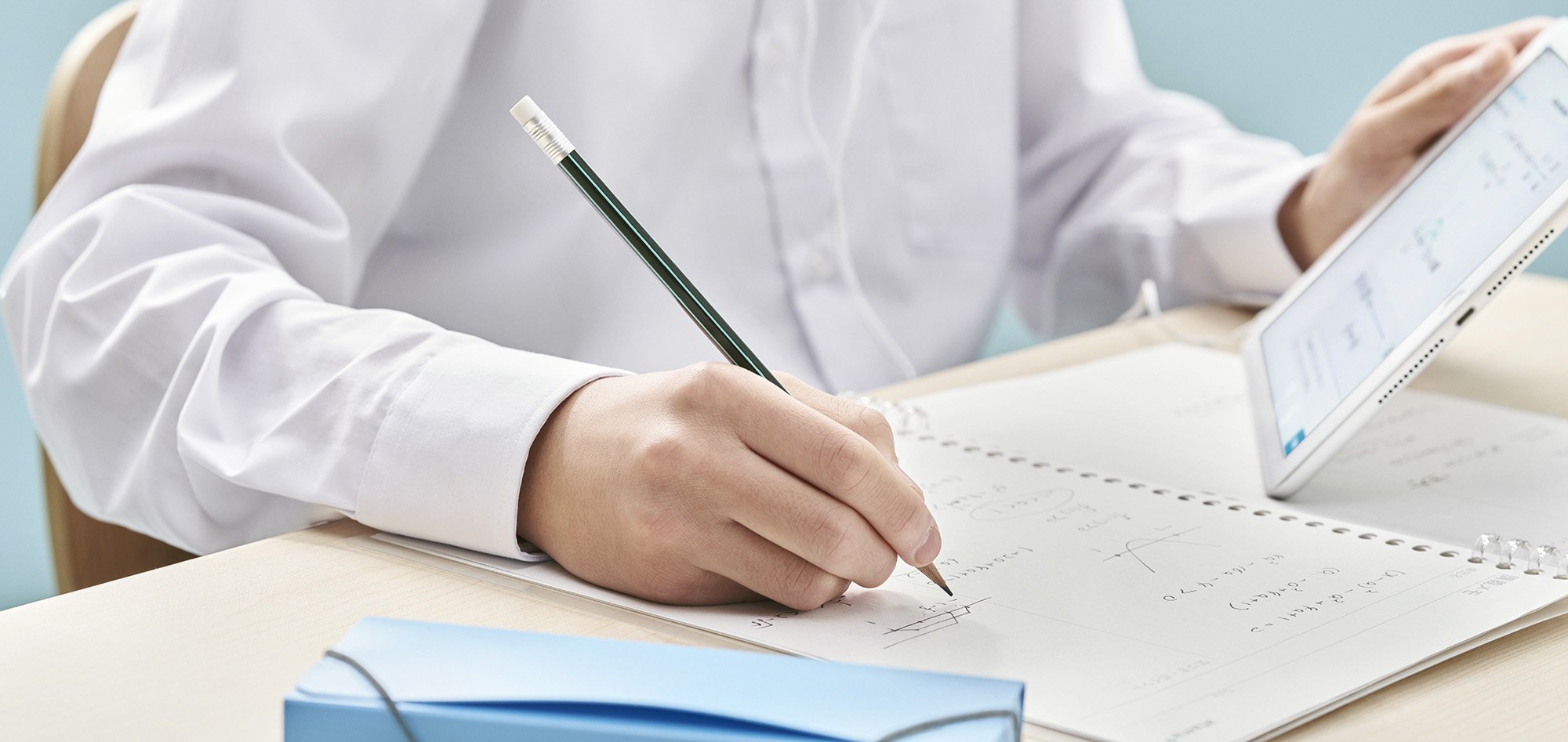2024.07.26
『天知る 地知る 我知る 人知る』
これは「後漢書」楊震伝の中に出てくる有名な言葉です。
後漢の楊震が賄賂 を断るときに言った言葉として今に伝えらています。
他人は知るまいと思っても、天地の神々も、自分も、それをするあなたも知っているんだぞと。
深いですね。
世界にはいろいろな諺があります。
そして、グッとくる言葉ってたくさんあるのですね。
上の言葉は、まぁ、「悪いことやって誰も見てないと思っても、きっと誰かに見られているし、いちばんは、自分自身がその悪事を働いてしまったことを知ってるじゃないか」
そんな感じでしょうか。
きっと海へ行けば、地平線のかたなに入道雲が立ちのぼっていることでしょう。
そんな猛暑続きの7月も後半、あとわずかで終わりです。8月は盛夏と言われますが、今よりも気温が高くなるのですか・・・。
教室ではとにかく授業中であっても水分摂取しながらエアコンもしっかりと作動させて運営中です。
このところ、帰宅したらすぐに 水のシャワーを浴びています。
その水もなんだか 冷たさが イマイチなんですよね。水道管も地熱でこもってしまっているのでしょう。
シャワーを浴びて、晩酌?
いえ、私はお酒ほとんど飲みません。
飲む習慣があまりないのですが、たまに「泡盛」という種類のお酒を水とか炭酸水で割って飲みます。
なぜ泡盛かというと、カロリー的なものです。
あれって、30度とか25度ありますので、けっこう薄めないと飲めないですね!
お酒好きな人から見たら、私の飲み方は、ヘタレです。
さて、本題です。
「夏」
「夏の学習」
学校が休みだから夏休みです。夏休みなので学校の授業進行がストップします。まぁ、補習とかがある場合もありますが、
ストップするということでいいでしょう。
ストップするということは、待ってくれていると考えれば
追い付くチャンス、追い抜くチャンス!!
こうシンプルに考えてほしいのです。
学校がスタートしたら、一日の多くの時間を学校で過ごし、5時間授業、6時間授業をこなすなかで、どんどんまた進んでいくわけです。
遅れてしまった、わからなくなってしまった、これを放置すれば
本当に勉強嫌いになってしまいます。
勉強というカテゴリは、別に 5教科学習がすべてじゃないんです。大人になる過程で、様々な学び要素があります。
例えば、パソコンの使い方を「学ぶ」でも
車の運転の仕方を「学ぶ」でも
ギターの弾き方を「学ぶ」でも
全部学びです。
これらは、つまづいたら わからなくなったところまで自然に戻りますよね。
その感覚で楽しく進めばいいのです。
勉強は できなくなるから つまらなくなるのです。
「夏」は 取り戻すチャンス!!
遊びもやってください。でも勉強もやってください。
アレもコレもと追えますよ。
何故って?
学校が休みだから たっぷり時間があるでしょう。