東船橋教室のメッセージ
小学5年生の算数、「工夫して求める」問題が子どもたちを悩ませる!
2025.06.25
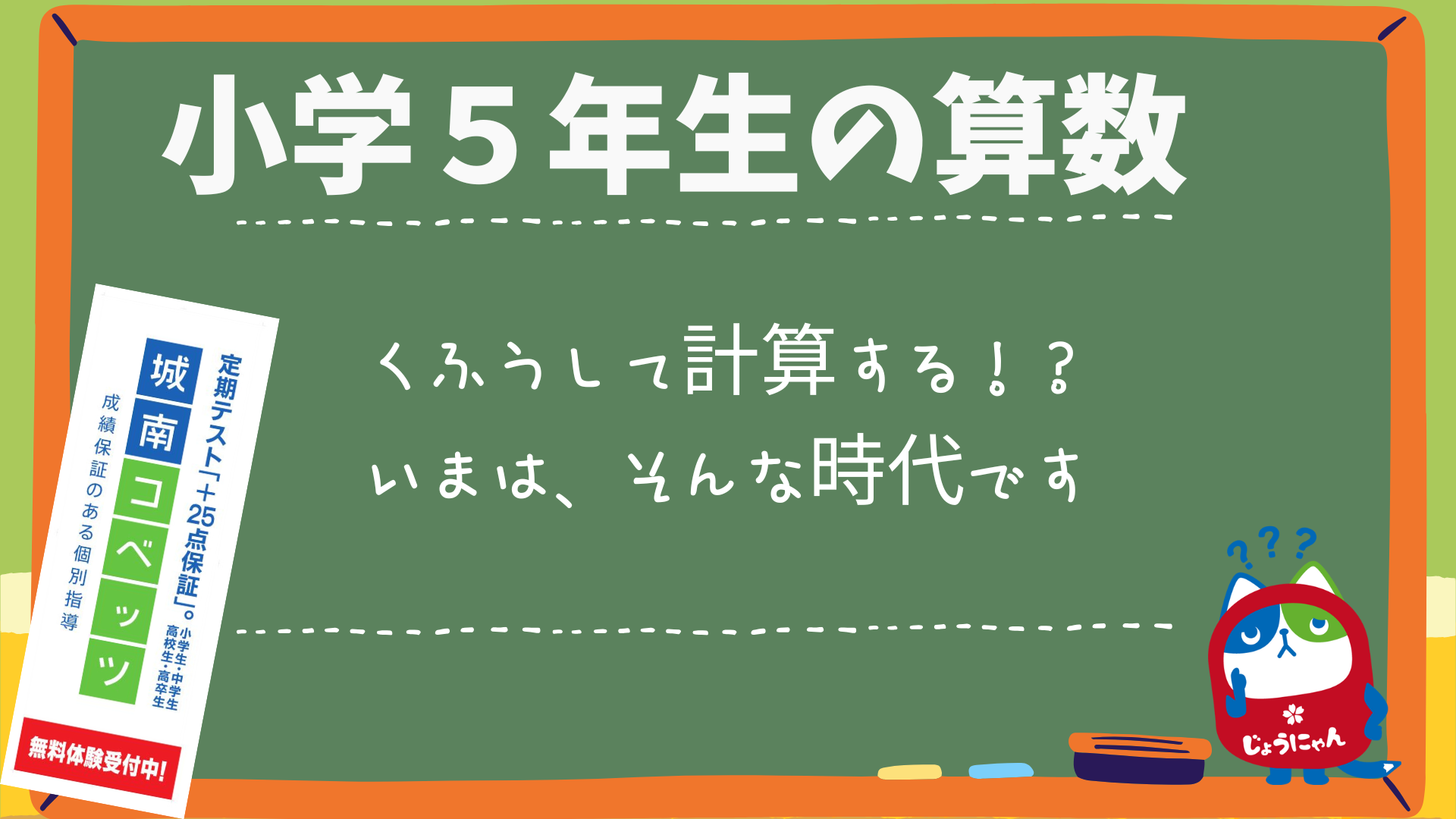
2025年6月25日(水)朝からザーザーと雨です。(もうすぐやむかな?)
東船橋駅周辺にお住まいの保護者の皆様、おはようございます!
城南コベッツ東船橋教室です。
新学年が始まり、まもなく2か月になりますね。
お子様の学習状況はいかがでしょうか?
今日は「小学5年生の算数」にちょっと絞ってみていきましょう!
小学5年生の算数では、新しい単元が増え、内容も一段と深まっています。その中でも、保護者の皆様が「これ、どう教えたらいいの?」と頭を抱え、お子様も「なんでこんなことするの?」と悩んでしまう問題があります。
それは、「工夫して求めなさい」という指示が付いた計算問題です。
「工夫して求める」って、結局どういうこと?
例えば、小学5年生で学習する小数のかけ算で、このような問題を目にすることがあるでしょう。
これを見たお子様の多くは、左から順番に計算を始めるはずです。
もちろん、この計算自体は間違っていませんし、答えも合っています。
しかし、「工夫して求めなさい」という指示がある場合、この計算方法では「工夫」ができていないと見なされてしまうことがあります。
いえ・・・・見なされてしまいます。
では、「工夫して求める」とは一体どういうことなのでしょうか?
それは、計算の順序を変えたり、計算のきまり(法則)を利用したりすることで、より簡単に、効率的に答えを導き出すことを指します。
上記の例で言えば、
を、
とするよりも、
というように、先に を計算して を導き出し、それに をかけることで という答えを出す、といった方法が「工夫」とされます。
あるいは、
これは決して悪い計算ではありません。
ただ、「工夫」のポイントは「掛け算の結合法則」を理解しているか、という点です。つまり、 は でも でも、あるいは でも結果は同じになるという法則を理解しているかを問うているのです。
特に、
という計算は、多くの「工夫して求める」問題で頻繁に登場する「鉄板」とも言える組み合わせです。これを知っているかどうかが、計算を簡単にするかどうかの分かれ目になることも少なくありません。
なぜ「工夫」が必要なのか?
「別に普通に計算しても答えが出るなら、工夫なんてしなくていいじゃないか」
ドヨヨ~~~~ン!
実は私も同感です。
しょーーーじき、同感です。
でも 今の教育は「先を見据えているので、それではダメ」なのです。
実際、お子さんもそう感じているかもしれませんが、子供は素直です。工夫して計算するという手法を必死に理解しようとしますし、がんばる姿を見せてくれます。
教科書で「工夫して求めなさい」という問題が出題されているのは、いくつかの理由があります。
-
計算力を超えた「数的感覚」を養うため ただ闇雲に計算するだけでなく、「どうすれば楽に計算できるか」を考えることで、数字に対する感覚が磨かれます。これは将来的に、より複雑な問題を解くための土台となります。
-
論理的思考力を育むため 「どの順番で計算すれば簡単になるか」「どのきまりを使えば効率的か」といったことを考える過程は、まさに論理的思考力のトレーニングです。
-
計算ミスを減らすため 複雑な計算ほどミスは起きやすくなります。簡単な形に変形することで、計算量が減り、結果としてミスの可能性も低くなります。
-
数学的な「美しさ」を理解するため 数学には、効率的で美しい解法が存在します。「工夫」を通して、そういった解法の「美しさ」を感じ取るきっかけにもなります。
「工夫」を身につけるためのステップ
では、お子様が「工夫して求める」問題に自信を持って取り組めるようになるためには、どのようなサポートが必要なのでしょうか?
ステップ1:計算のきまりをしっかり理解する
まずは、算数で学ぶ基本的な計算のきまりをしっかりと理解することが重要です。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
- 交換法則: 足し算やかけ算では、計算する順序を変えても答えは同じになる。
- 結合法則: 足し算やかけ算では、3つ以上の数を計算するとき、どの2つを先に計算しても答えは同じになる。
- 分配法則: かけ算と足し算(または引き算)が混ざった計算で、カッコの外の数をカッコの中のそれぞれの数にかける。
-------------------------------------------------------------------------------------------------↑
これは、中学でも登場しますし、用語も大切ですから、良かったらお父さん、お母さんも一応覚えておくといいかもしれません。
これらのきまりが、まさに「工夫」の土台となります。
ステップ2:具体的な「工夫」のパターンを学ぶ
次に、よく使われる「工夫」のパターンを具体的に知ることが有効です。
-
キリの良い数を作る のように、かけ合わせると や といったキリの良い数になる組み合わせを見つける練習をします。 例:
-
共通する数でまとめる(分配法則の逆) のような問題では、共通の でまとめると、 となり、簡単に計算できます。
-
数を分解して考える のような問題では、 を と考えて、 といった計算ができます。
↑
この3つは、すごく重要です。特に2つ目の「分解法則の逆」と「数を分解して考える」パターンは、会得しておくと、ワンランク上のお子さんになってきます!
ステップ3:繰り返し練習し、成功体験を積む
これらの知識をインプットしたら、あとは繰り返し練習するのみです。最初はうまくいかなくても、様々なパターンの問題に触れることで、「もしかしたら、この方法が使えるかも?」という気づきが生まれてきます。そして、工夫して解けたときの「できた!」という成功体験が、お子様の自信につながります。
城南コベッツ東船橋教室で「算数の壁」を乗り越えよう!
城南コベッツ東船橋教室では、お子様一人ひとりの学習状況に合わせた個別指導を行っています。
「工夫して求める」問題で悩んでいるお子様に対しては、
- 計算のきまりを丁寧に解説し、根本的な理解を深めます。
- 「キリの良い数」の組み合わせなど、具体的な「工夫」のパターンを実践的に指導します。
- お子様が自力で「工夫」を見つけられるよう、段階的にヒントを与えながら思考力を養います。
- 豊富な演習問題を通じて、定着度を高め、自信へとつなげます。
「うちの子は算数が苦手だから...」と諦める必要はありません。小学5年生の算数は、中学校以降の数学の土台となる重要な時期です。この時期に「工夫」の楽しさや論理的に考える力を身につけることは、お子様の将来の学習において大きな財産となります。
無料の学習相談も随時受け付けておりますので、「工夫して求める」問題だけでなく、算数の学習全般についてお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
東船橋駅近くの城南コベッツ東船橋教室で、お子様の「わかった!」という笑顔に出会えることを楽しみにしております。






